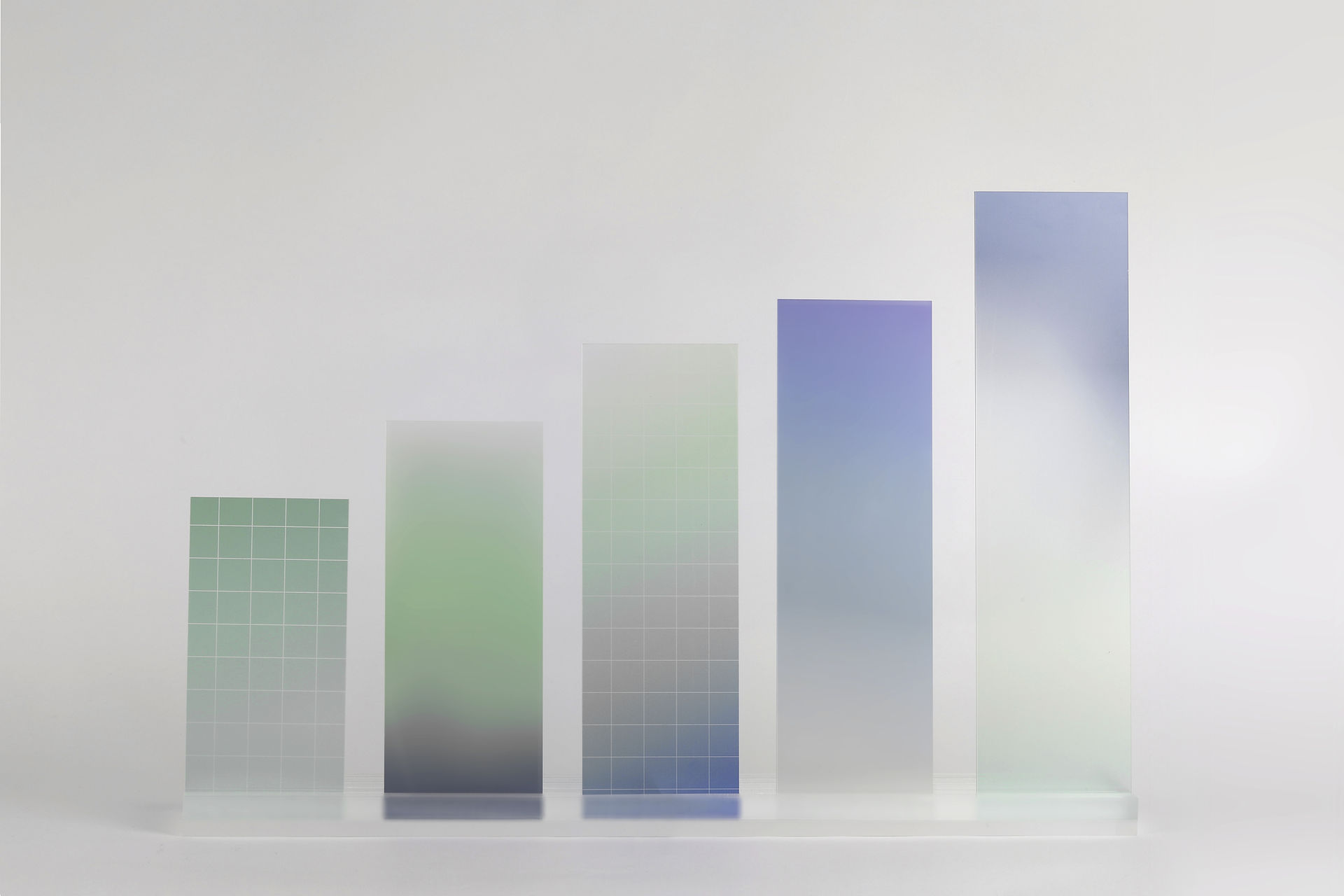目のこと
9月のワークショップでも、目と全身との関わりについて、その重要性をお話をさせて頂きました。 シンプルに考えると、目も筋肉の動き。 「見る」という単純な動作の中にも様々な癖を生み出し、全身の機能に影響を与えています。 今回、視野欠損の症状で長い間治療を受けていらっしゃるピアニ...
2018年9月28日


ワークショップを行って
9月11日と12日のワークショップ。 多くのピアニスト・声楽家・ヴァイオリニストさんがお集まりくださいました。 いつも冒頭にフェルデンクライスの特長について説明をさせて頂くのですが、 今回は「他のメソッドとの違い」について、としました。...
2018年9月26日


カラダから考える音楽 指から肩・肩から首
ワークショップ3つ目のキーワードは 「指から肩・肩から首」 他のキーワードとは違い、具体的な部位にしました。 やはり、一番気にして使う部分。色々と感覚を明確にしたいものです。 このブログでも、何度も呟かせていただいておりますが...
2018年9月8日