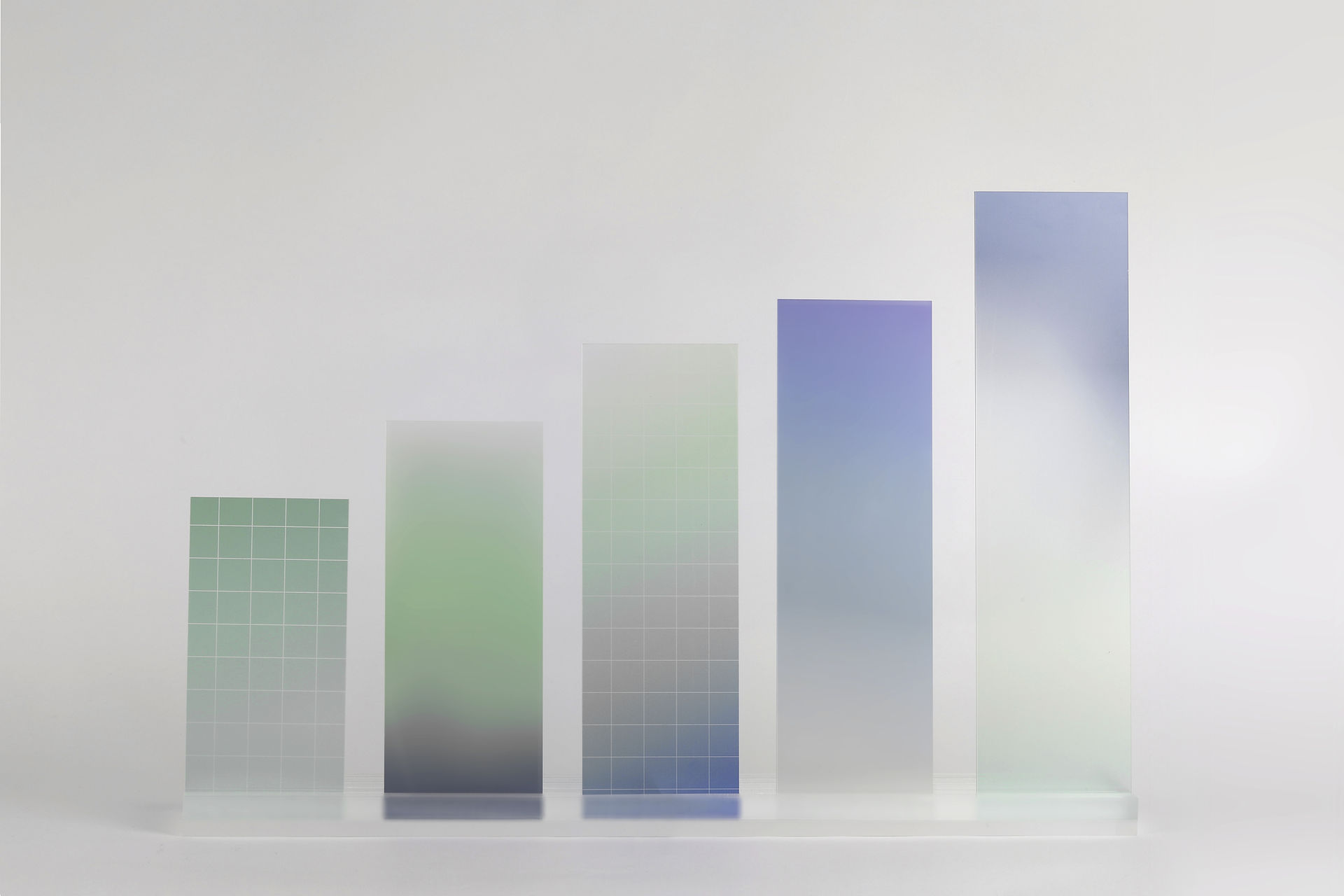指くぐりの可能性
スケールやアルペジオなどの基本的な動きへのフェルデンクライス的アプローチは 楽しく実践をしながらすすんでおります。 2.3.4の指の動きについては、骨格のもつ動きを意識しながら、いかに肘や肩、さらに骨盤まで動きの伝達を感じられるかということに時間を費やしますが、やはり...
2016年6月26日
ジストニアの方へのレッスン
最近ジストニアを発症されてしまった方々が多くレッスンにお越しになっています。 ジストニアについては、研究機関やその他多くのサイトで説明のとおり、症状は人それぞれです。 レッスンは症状を見ながらとなりますが、基本的には指先の感覚を上げることを優先としています。 ...
2016年6月11日
スケールを弾こう
スケールのワークショップを行っています。 スケールはピアノ奏法の基本ですが、実に奥が深いものです。 ついピアノと接触している指先に集中してしまいますが、腕や体のコラボレーションも不可欠です。 指を動かすことも、個々の習慣によって人それぞれです。習慣から抜け出して効率の良い...
2016年6月10日