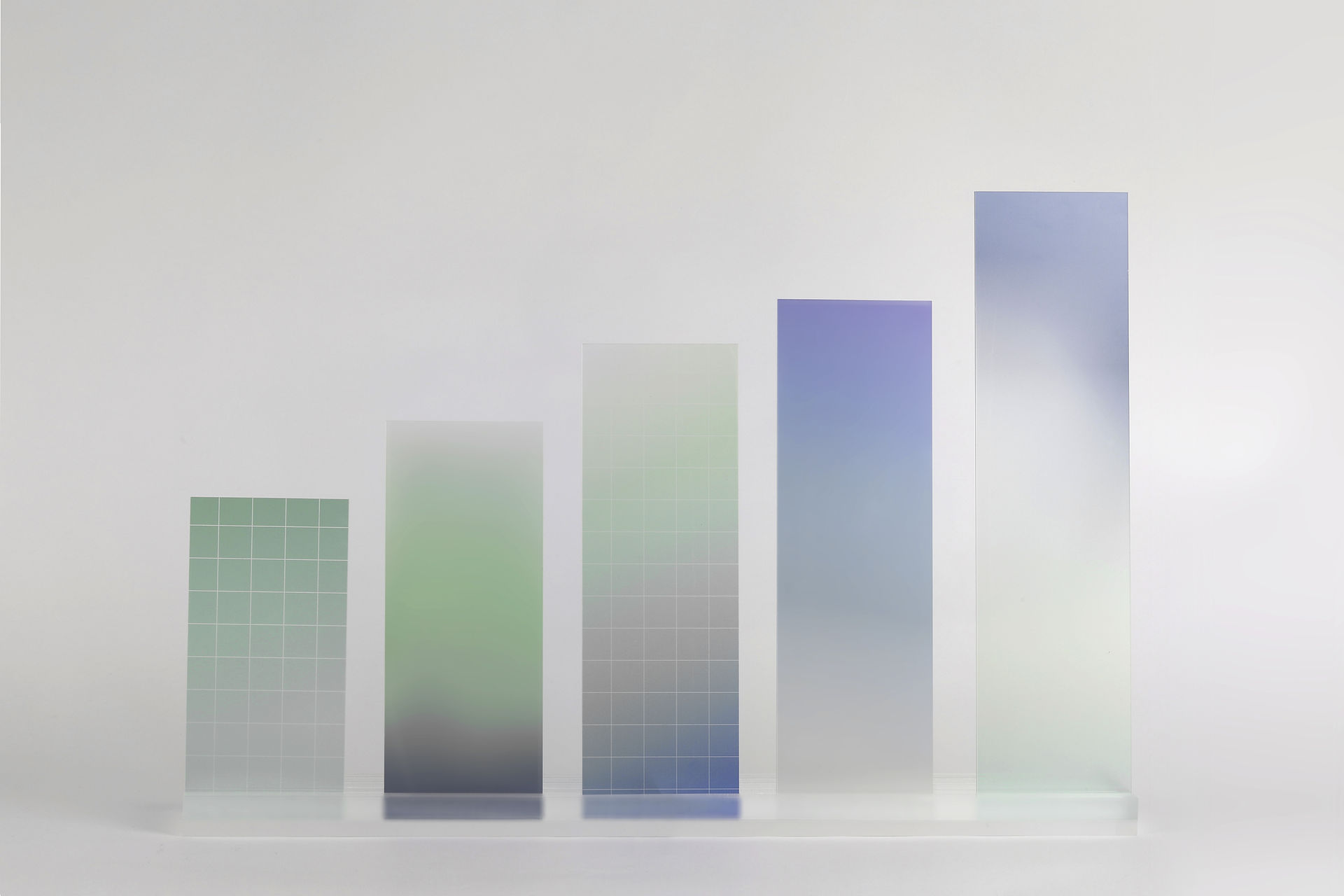プラクティショナーになろう
フェルデンクライスをやってからよく思うのは、ピアノの演奏がいかに運動であるかということ。 追求するものは芸術なんですけど〜。 大きな音を出すためにも、本当にいろいろな体の使い方を私たちはしていて、出せる人と出せない人がいる。それは単に骨格の違いだけではなく、体の使い方の違い...
2018年10月15日


手首を落とす・回すを考える
ピアノ導入書で時々目にする 「手首を落とす、手首を回す」 これをどのように指導したら良いですか?と先日ご質問いただきました。 ピアノの世界では「脱力」という一種のマジックワードがあって、「脱力が出来てないのが全ての原因では?」と多くの人を悩ませています。...
2018年10月5日