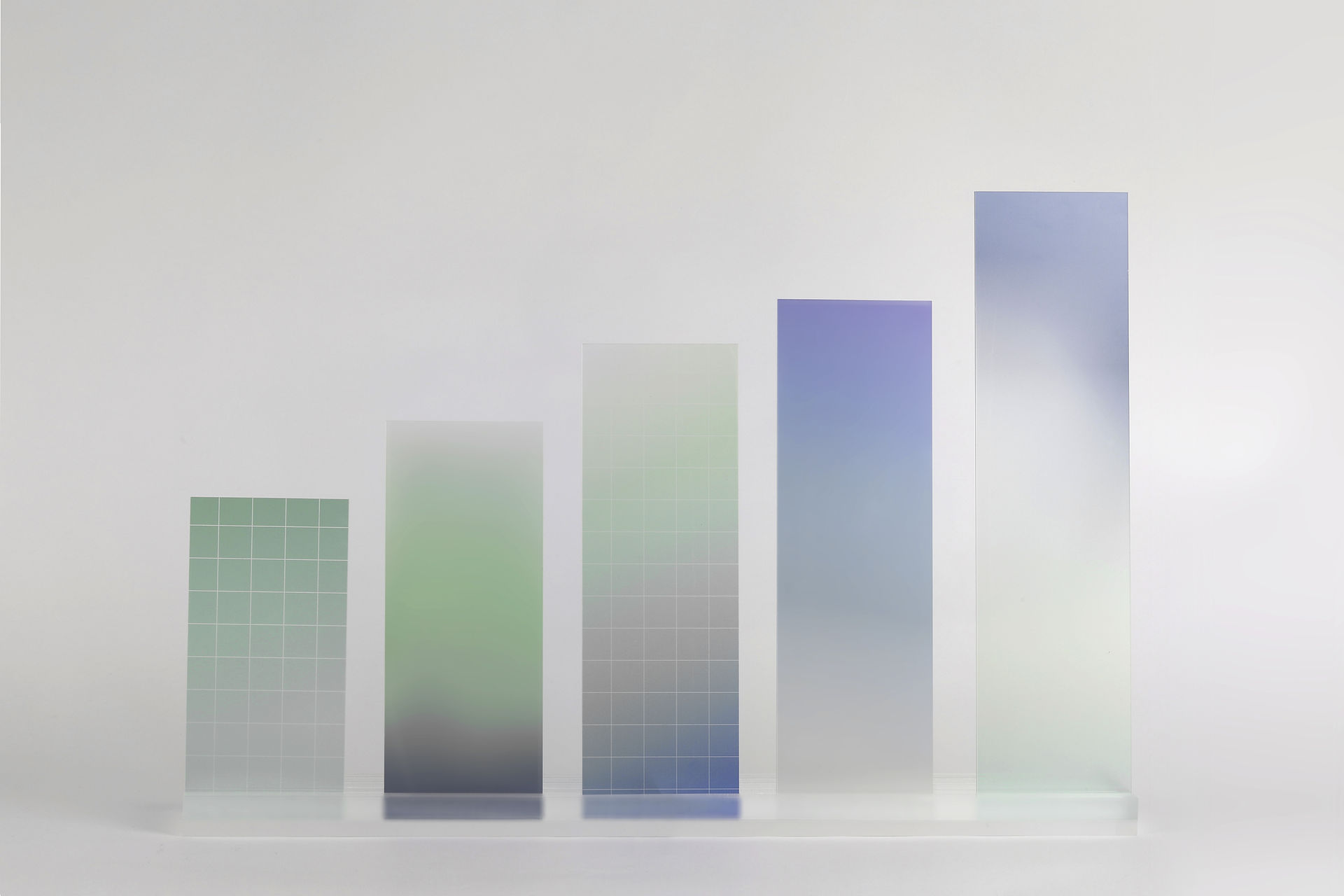
フェルデンクライスメソッドとピアノ演奏への活用
モーシェ・フェルデンクライスとそのアイデア

Courtesy of Feldenkrais Institute,
Tel Aviv, Israel
モシェ・フェルデンクライス(Moshe Feldenkrais,1904-1984)
ロシア生まれの科学者モシェ・フェルデンクライスにより体系化されたメソッドで、身体の機能の改善を目的とする学習システムです。
物理学博士でありながら、機械・電気工学、心理学に柔道などあらゆる分野に精通したフェルデンクライスが、身体の機能や発達メカニズムに興味を持ち、その後このメソッドの開発に至ったのには、彼自身の膝の大怪我が起因となりました。体の機能と脳との関わりを探求し続けた結果、医師の予想に反して彼は見事に怪我から復帰したのです。
その後一つのメソッドとして体系化され、ヨーロッパ各地・アメリカなど全世界に広まっていきました。年齢や身体上の制限なく取り組めるメソッドで、その応用力の広さから、脳や身体機能の障害といった医療や介護の分野から、芸術・スポーツ・ダンス・演劇など様々なフィールドで導入されています。
人が動きを学ぶとは…
■ 習慣と癖
例えば「立ち上がる」というシンプルな動き。人によって様々であると思いませんか?よいしょ、と足を踏ん張って立ち上がる人。重さを感じさせずにすっと立てる人など。
その違いは何でしょうか?
赤ちゃんの時は皆同じなのに、成長と共に「習慣」「癖」が動きの中に生まれていきます。
足を踏ん張る方は、特定の筋肉に力を入れて立ち上がる習慣があり、軽やかに立ち上がる方は全身をしなやかに使う方法が習慣化されているのかもしれません。
■ 方法論で正しい動きを学ぶ?
そもそも何が「正しい」のか、定義することは難しいものです。
足の構造を学び、動きのメカニズムを理解したところで人によっては、足を上げるために背中を固めているかもしれないし、腹筋にも無駄な力を入れる人がいるかもしれない。要するに力の入れ方には目に見えない「習慣」が潜んでいるのです。ですので知識や動きの真似から学ぶことには、少々注意が必要です。
■ 好奇心から学ぶ
結論としては、自分の動きを見つめ直し、自分で発見していくのが理想です。
体のパーツを動かすために、全身のどの部分が関わっているのか探していきます。探索が深まるごとに動きが変化していく感覚、そして楽になっていく感覚が深まってくると、頭がとてもワクワクした状態になります。もっと探したい!という好奇心です。
この好奇心こそが学習の本質です。
■ ATMとFI
フェルデンクライスメソッドで必ず耳にするのが「ATM」「FI」という二つのアプローチ法。この詳細については、フェルデンクライス・ジャパンの公式サイトをご参考に!ピアノへの活用でも、時としてその両方を行いますが、FIについては、ピアノを弾く動きの中に多く組み込んでいます。
ピアノ奏法への活用
フェルデンクライスメソッドは、身体的な動きと感覚の意識を高めることに焦点を当てたトレーニング法です。
音楽家にとって、身体の調整や感覚の高め方は演奏技術の向上に重要な役割を果たします。
■習慣から離れてクリエイティブな動きの発見
ピアノは長い年月をかけて習得するので、多くの習慣による動きが大半を占めてる状態です。
まずは感覚を得るためのセンサーを研ぎ澄ませるアプローチから。わずかな違いを感知できる感覚を取り戻しつつ、新しい理にかなった動きを探していきます。ピアノ演奏時の自分の動きをしっかりと感じながら、指や腕の動きの中にこれまでと違った動きを探しましょう。
フェルデンクライスメソッドは、自己探究に基づくトレーニング法でもあります。
これまでと違った動きやスキルを見つけ出すことは、演奏技術だけでなく創造性や表現力に対しても重要な要素のように感じます。
■姿勢の改善
フェルデンクライスメソッドは、自分自身の身体感覚に注目することで、身体の状態を改善することを目的としています。
演奏中でも快適な姿勢を見つけ出すことはとても重要なことです。このメソッドを通じて自分自身の身体感覚を高められることで、自分自身の姿勢や動きに対して自然な調整を行えるようになります。
■動きの柔軟性と効率の向上
身体感覚が高められることで、動きの柔軟性と効率を高めることにも役立ちます。
演奏に必要な動きをより柔軟に、より効率的に行うことができるようになることは、演奏技術の向上につながります。
